ボクが越境できたわけ
1人でも、まずは見える化から始めてみる
新井剛氏が最初に投げかけたのは、プロジェクトや組織、会社でモヤモヤした問題を抱えていないかという一言。具体的には「チームと言いながらメンバー同士で何をしているのか、何が課題か、まったく分かっておらず共有もされていない」という問題だ。
皆さんの中にも、同様の状態に置かれている人がいるだろう。昔は協力しお互いのことを知ろうとしたが、次第に周囲の雰囲気に飲み込まれ、いつしか「どうしようもない」と諦めてしまったかもしれない。そんな人にこそ『カイゼン・ジャーニー』を読んでもらいたいと新井氏は強調する。
いまやヴァル研究所は社内見学を行うほど模範的な会社として知られているが、新井氏もかつて同じ経験をしたという。そこで職場を離れる選択肢もあった。しかし、会社を変えていこうと決意し、さまざまな改革に取り組み始めた。
とりわけ重視するのが、会社の課題や仕事のプロセスなどを見える化する仕組みを作ること。『カイゼン・ジャーニー』でも最初に解説される方法論、タスクマネジメント、タスクボード、朝会、ふりかえりの4つが肝になったという。
タスクマネジメント
何か仕事を始めるとき、前もってタスクの目的と規模、段取りを明確にしておくこと。計画が立てやすくなり、リソースやスケジュールの問題が明らかになる。
タスクボード
タスクの状態(遂行具合)を見える化するためのもの。専用ソフトや実際のボードや付箋を利用して日々の変化を俯瞰することで、問題を早期発見できる。
朝会
タスクの状態の変化を反映するタイミング。毎朝決まった時間に行い、計画とのズレを検出し、その日やるべきことを整理する。
ふりかえり
仕事のやり方や結果を見直し、次の計画や業務に活かすことを目的とした活動。時間がないと疎かになりがちだが、仕事をよりよくするために最も重要だと言える。
※『カイゼン・ジャーニー』を参考にした。
この見える化が進むことでタスクや課題をチームメンバーと共有できるようになるが、最初から協力して取り組めるなら問題はない。新井氏が提示した問題とは、こうした方法論すら誰にも関心が持たれないような状態を指す。
新井氏もそうだった。だから、1人から始めた。「ぼっちでもできることがある」と、まずは自分でやってみることが大事なのだと何度も繰り返されていた。そして自分が効果を感じ始めたら、少しずつ周りを巻き込んでいこう。
1人から2人へ、そしてチームへ
では、どうやって周りを巻き込むのか。新井氏は社内勉強会を挙げた。『カイゼン・ジャーニー』でも、主人公はどうやって1人だけの状態から進んでいけばいいのか悩む。そのときたまたま隣に座っていた、世間話をするような仲の同僚に社内勉強会をやってみようと声をかける。
ただ、そうは言ってもただの勉強会だと誰も来ないかもしれない。新井氏は、社外から講演者を招くことを勧める(しかもちょっと名のある人)。そこで社内の人に興味を持ってもらえれば、そこからより前進させていくことができるだろう。
1人から2人へ、そしてチームへと意思疎通ができ一体となることができ始めたら、チームで仕事をするための方法論が必要となる。そこで新井氏が提案するのがバリューストリームマッピングとモブプログラミングだ。
バリューストリームマッピング
プロダクトの価値が顧客の手に渡るまでの仕事の流れを見える化する方法。開発が滞りなく動いているのかを確認でき、無駄な作業や停滞している原因を把握できるようになる。その解決のためにチームで議論を行う必要があるので、コミュニケーションツールとしても役立つ。
モブプログラミング
参加者全員で一つの画面を見て議論しながら作業する手法で、チームや新しいメンバーが学ぶべきことがあるとき、モブプログラミングを行うと非常に高い学習効果が得られる。コミュニケーションの改善や、チーム全体で達成感を共有できるというメリットもある。
※『カイゼン・ジャーニー』を参考にした。
そうして社内の仲間ができたら、今度は社外の仲間を作っていく。モブプログラミングも有効だし、社外の勉強会への参加や会社見学ツアーを行っても面白い。どんどん越境していくことが、よりよい現場を作っていくことになる。
何かをやろうと決めたその波紋が何かを生む
できない理由はいくらでもあるし、時には問題を放置しておくことも必要かもしれない。しかし、何かをやろうと決めると、そこから波紋が生まれ、他者に影響を与えていく。たとえ自分自身に見返りがなくても、次世代に恩恵を受ける誰かがいるかもしれない。それがエネルギー源になる、と新井氏は言う。
そして最後に、大事なポイントを5つを挙げた――自分から始め、越境し、フィードバックを得て、リフレーミングが起こり、仲間に巻き込み巻き込まれる。そのサイクルがあなたのカイゼン・ジャーニーとなる。
本書『カイゼン・ジャーニー』を旅の相棒としてほしい、と新井氏の講演が締めくくられた。

右 市谷聡啓氏:ギルドワークス、エナジャイル
世界を変えるにはどうしたらいいか?
問いから始めよう
『カイゼン・ジャーニー』の表紙にある「Can we change the world?(世界を変えるにはどうしたらいいか?)」は、市谷聡啓氏の原点、「立ち返りの問い」となるフレーズだという。ただ、世界といっても広く、どのあたりなのかというと、「他者と共有できる目的(Why)のある世界」を指すそうだ。
市谷氏は何事も「問いから始めよう」と言う。そして、その問いがまだ誰も手を出していないものなら、越境が必要だと。
越境とは何か? 目的のために、役割を選ばず、あらゆる人を巻き込み、あらゆる手段を取り、目的を問い続けることだ。この越境のサイクルを回すことが、目的を達成するために必要だという。
越境のサイクルは「立ち返りの問い」から始まる。自分が正しく歩めているのか、時々で振り返らせるための問い。これに対する答えが目的(Why)となる。
例えば『カイゼン・ジャーニー』では、主人公は「自分は何者なのか」という問いを強く突きつけられる。そこから「何者か答えられるようになりたい(物語のうえでは、それは絶望的な現場を変えることに等しい)」と考えるようになる。つまり、それが問いに対する答え(目的)となる。
しかし、そもそもどうやって「立ち返りの問い」を見つければいいのだろうか。市谷氏は、まずは自分の意思(Will)を見つめ直すことだと言う。つまり、何をしたいのかということだ。
何をしたいのかが分かれば(実はこれが難しい)、なぜそれをしたいのかを考えられる。それがすなわち、目的である。その目的が答えとなる問いこそが、「立ち返りの問い」だ。ただし、その問いが意思と合致しているかは検討しなければならない。
再び『カイゼン・ジャーニー』の主人公を例に取れば、彼の意思は「現場を変えたい」ということ。なぜそうしたいのか? 現場をワクワクする場所にしたいから。それが答えとなる問いは「理想の現場になっているか?」。これは意思と合致している。そして問いが確固たるものであればあるほど、意思は一つでなくてもいいことに気づける。
問いに少しでも答えることから始めよう
問いが見つかった。では、何から始めればいいのか。市谷氏は「立ち返りの問い」に少しでも答えることから始めようと言う。ただし、4つの注意点――考えすぎない、準備しすぎない、計画しすぎない、一気にやらない――がある。
考えすぎない
何が正解なのか、事前に考えすぎると最初に一歩すら踏み出せない。合っているかどうかはあとで検証しよう。検証するための基準や原則も『カイゼン・ジャーニー』から借りてくればいいとのこと。
準備しすぎない
最も貴重なリソースは時間だ。何事を始めるにも「まずはしばらく勉強してから」と思う人がいるかもしれないが、それでは時間がもったいない。最高のタイミングを待っているほど人生は長くないのだ。
計画しすぎない、一気にやらない
市谷氏は下手に計画を広げず、実用的で最小限の作戦から始めるべきだと強調する。いきなりボス戦に向かうのではなく、経験値を貯めて仲間を集めよう。つまり、新井氏が言うように、1人から始め、そのあとチームで取り組み、さらにチームの外を巻き込んでいくべきなのである。
こうして「ふみだす」ことができたら、次は成果を「あらわす」必要がある。成功も失敗もすべて成果なので、その経験を周りに伝えていこう。あなたが伝えなければ誰にも伝わらず、熱意も伝播しない。
そして次に「まきこむ」フェーズとなる。人は多くの場合、巻き込まれるものだ。周りの人と共有できる目的(Why)であれば、そこから人は巻き込まれる。また、巻き込まれやすくなる入り口を用意していく必要もある(一緒に社内勉強会を企画しよう、など)。もし共感を得られなかったなら、「立ち返りの問い」に戻って考えよう。
市谷氏は「世界は、ただあなたが戻ってくるのを待っている」というメッセージを掲げ、講演を終えた。
『カイゼン・ジャーニー』とは
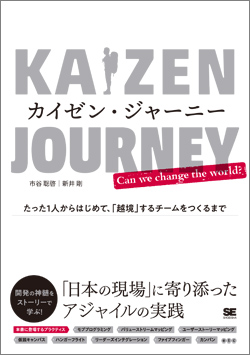
本セッションのベースとなった『カイゼン・ジャーニー』は、隣の席の同僚が何をやっているか分からない、とりあえず目の前の作業だけをやっている、誰もプロジェクトの全体像を把握していない――そんな現場を変えていきたいと思う人のための1冊。
主人公・江島がどうしようもない空気の漂う現場を改革していくストーリーが描かれ、シーンに応じてプロジェクトを効率よく進めていくためのプラクティスやノウハウが登場、随時解説されていく。
江島が置かれているほど絶望的な状況でなくても役立つ方法論が紹介されているので、ぜひ参考にしてみてもらいたい。



