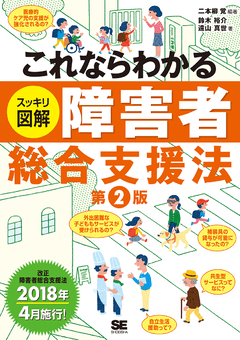常時介護を必要とする人たちのサービス
3障害を対象とした制度へ
前項で、居宅介護は地域生活を支える骨盤のようなもの、という話をしましたが、障害の程度によっては、居宅介護のサービス内容では不十分な方も多くいらっしゃいます。特に、1人で行動することがほとんどできない重度肢体不自由者は、ほぼ丸一日介護の必要がある場合もあります。
そのような人たちが地域で生活を送るための制度が「重度訪問介護」です。障害者自立支援法(以下、自立支援法)の時代は、重度訪問介護は一部肢体不自由者のみに限定されていました。しかし、平成26年の法改正では、3障害すべてを対象とした制度に生まれ変わりました。また、平成30年の改正で、訪問先が医療機関まで拡大されたことにより、医療機関に入院した場合でも、利用者の状況がよくわかっているヘルパーを継続的に利用できるようになりました。

重度障害者の手足の代わりに
居宅介護が短時間での支援とすると、重度訪問介護は、長時間の利用を想定した制度となっています。報酬単価も8時間までを基本と考えて、24時間利用できるように制度が組まれています。まさにヘルパーが重度障害者の手足の代わりとして生活を支えるといってもよいでしょう。

障害特性に応じた支援
知的障害や精神障害の場合、肢体不自由者が必要とする介護とは異なり、直接的な介護が必要というよりも、激しい自傷や他害行為、集団行動の困難などの行動障害によって介護が必要という場合が多く考えられます。そのため、行動障害に対する支援方法について新たな研修を設定するなど、障害に応じた対応が取れるように設定されています。また、支援計画を作成する際には、アセスメントで本人の特性や強みなどを把握して、場面や工程ごとに丁寧な計画を作ることが必要です。