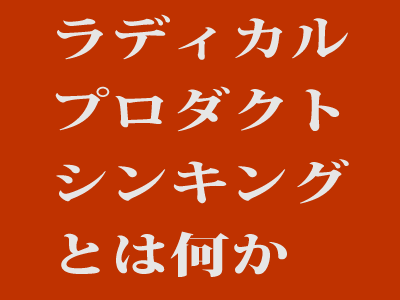本記事は『ラディカル・プロダクト・シンキング イノベーティブなソフトウェア・サービスを生み出す5つのステップ』(ラディカ・ダット)の「序章 ラディカル・プロダクト・シンキングとは何か」を抜粋したものです。掲載にあたって一部を編集しています。
ビジョンよりも目先のことを優先してしまう現実
1世紀以上にわたって、世界を変えるほど画期的なプロダクトをつくるのは、ヘンリー・フォード、スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツ、リチャード・ブランソンなどといった、ほんの一握りの先見の明のある野心家たち、いわゆるビジョナリーの特権だと考えられてきた。
そうした例外的なリーダーたちは巨大なゴールを設定して、そこにたどり着くための方法も知っているともてはやされ、ビジョンに導かれて成功を収める才能を生まれつき持ち合わせているのだと思われていた。
彼らリーダーはビジョンがあったからこそ、世界を変えるほどのプロダクトをつくることに成功した。そこで多くの企業がこの点を見習い、ビジョンステートメントを作成するようになった。しかし、あるアイデアを構想から実現にまで導くのはどうやらかなり難しいようで、画期的なプロダクトを世に送り出すことに成功した企業(あるいは個人)はわずかでしかない。
ビジョンを追うことが大切だとわかっているのに、私たちはついつい同じことを繰り返してしまう。組織内でイテレーティブ(反復的)な活動に陥ったことのある人なら、自分が目先のことばかりに意識を奪われ、結果的に大きな機会を見逃しているような気になったことがあるだろう。要するに、ビジョンをもつだけでは不十分で、大切なのはビジョン駆動型のアプローチを身につけることだ。そのためには新しいマインドセットが欠かせない。
ボーイング737MAXの欠陥
ビジョン駆動型のアプローチとイテレーティブ型のアプローチの違いを理解するために、ボーイング737MAXの開発を例に見てみよう。同機は2019年の3月に全世界で運行禁止になった。わずか5カ月のあいだに製造後まもない2機が立て続けに墜落し、346人の犠牲者を出したからだ。
ボーイング737が就航を開始したのは1968年のことだった。737を40年間つくりつづけてきたボーイングのエンジニアたちは、同機の時代が終わりに近づいていることに気づいていた。737は機体の高さが低いことが特徴で、貨物の積み下ろしが手作業だった時代にはとても好都合な長所だったのだが、近年ではそれが欠点になっていた。両翼の下に搭載するエンジンのサイズが限られるからだ。
すでに1990年代から、ボーイングは大型のエンジンを737に積もうと躍起になっていた。たとえば737ネクストジェネレーションと呼ばれるタイプの機体では低いフレームの下に設置するために、エンジンを卵形にする必要があった。
この時点で、ボーイングには長期的なビジョンを追い、737に取って代わるまったく新しい機体を開発する道を選ぶこともできただろう。しかし、新型機「ドリームライナー」の研究開発に数十億ドルを費やしたばかりだったこともあり、ボーイングは1970年代からベストセラーだった737がもたらす利益に頼りつづけた。同社の経営陣は、新しいナローボディ型の機体を求める市場の声への対応を先送りにしたのである。
この隙間を埋めたのがライバル社のエアバスで、燃料効率を20パーセント上昇させたA320neo型機を市場に投入した。ボーイングにとって最大にして最重要の顧客であるアメリカン航空がA320neoの導入を決めたとき、ボーイングは迅速な対応を迫られた。
そこで2011年8月、同社は既存の737の型を再利用して新型の737MAXを製造することにした。737をまたもアップグレードするという決断を聞いてエンジニアたちはうんざりしたが、短期的なビジネス目標を達成するにはしかたのないことと理解した。このイテレーティブな取り組みにより、新機種をゼロから開発した場合の半分の時間と10パーセントから15パーセントほどの費用で新機種をつくり、認可を得ることができたであろう。
しかし、737に大きくてパワフルなエンジンを積むのは容易なことではなかった。機体の低い737に合わせて、エンジニアはエンジンをアップグレードする必要があった。ところが都合の悪いことに、エンジンを変えると機体の挙動が不安定になった。機首が上を向きやすくなり、そのせいで速度が出ないのだ。
この問題に対処するために、ボーイングはMCAS(操縦特性補助システム)と呼ばれる自動失速防止機構を用いて、機体が失速しそうになったときに機首を下に向ける仕組みを追加した。しかし、ライオン・エアとエチオピア航空の飛行機が墜落し、346人の犠牲者を出したとき、このMCASが事故の原因として非難されたのである。
ローカルマキシマムか、グローバルマキシマムか
ボーイングは市場の圧力に屈して、イテレーティブなプロダクト開発の道を選んでしまった。737MAXの開発に際して、ボーイングはいわゆるローカルマキシマム(局所的な最適化)と呼ばれるものを見つけた。エアバスに主要顧客が流れていくことを防ぐための短期的な最適解を導き出したのだ。しかしながら、ボーイングはそのプロセスにおいて「安全で信頼性の高い飛行機をつくる」という最も重要であるはずの点を見落としてしまった。
ボーイングが本当に必要としていたのは、まったく新しい機体の開発への投資、つまりビジョン駆動型のアプローチだった。自社、利用客、そして各航空会社の3者にとって最適な長期ソリューション、いわゆるグローバルマキシマム(全体的な最適化)を目指すべきだったのだ。
ローカルマキシマムを見つけようとする行為は、たとえるなら、チェスで負けそうになっているときに一部のピースだけを眺めながら最善の手を考えるようなこと。対照的に、グローバルマキシマムを見つけるとは、チェス盤全体を眺めながら長いゲームにとって最高の一手を打つことを意味する。そのためには、自分が追い求めるビジョンと、それを実現するための計画が必要だ。
ボーイングはビジョンステートメントこそ発表していたが、肝心のビジョンがグローバルマキシマムのなかで語られるべき核心をついていなかった。イテレーティブ型のアプローチは多くの場合で、ビジネス目標にもとづくおおざっぱなビジョンにつながる。たとえば、「……分野で最高になる」や「……に革命を起こす」などだ。
2018年の『年次報告』でボーイングはこう宣言している。「我々の目的と使命は、航空宇宙技術のイノベーションを通じて世界を結び、守り、探索し、刺激することである。航空宇宙産業界で最高の企業となり、業界のグローバルチャンピオンの座に君臨しつづけることを目指している」。このような漠然とした意志表明は、旅に出るときに「さあ、北へ向かって最高の旅をしよう」と言っているようなものだ。
長期的なゴールを思い描くことができなければ、短期的なニーズに目を奪われ、そこに向かって進んでしまう。ボーイングは737の型を何十年にもわたって再利用することで短期的な業績に焦点を合わせただけでなく、2013年から2019年の第1四半期にかけて430億ドルを投じて株の買い戻しを行ったことで、利益も短期的に最適化した。
ドリームライナーをゼロから開発するのに、ボーイングは8年間で320億ドルを投じたと言えば、買い戻しの規模の大きさがよくわかるだろう。最高の旅をするという大まかなビジョンでは、焦点は目の前の目標にしか合わない。
しかしこれまでの長い年月、私たちはおおざっぱで野心的なビジョンがプロダクトと企業を成功に導く鍵だと学んできた。その際、短期目標への近視眼的な焦点も、ほぼ避けようのない当たり前のこととして受け入れてきた。調査によると、1980年代以降、全体的な傾向として、企業は短期志向の度合いを強めてきたそうだ。
組織計画の対象期間が短くなるにつれ、企業は短期的な利益を得るための投資機会を、つまりローカルマキシマムを探すようになった。
ゼネラル・エレクトリックが陥った罠
ゼネラル・エレクトリック(GE)の掲げた「参入しているすべての市場でナンバー1か2になる」という目標がそのようなビジョンの模範とみなされた。CEOになってすぐ、ジャック・ウェルチは「成長の遅い経済で迅速に成長する」というタイトルでスピーチを行い、「GEは牽引される列車ではなくGDPを引き上げる機関車となる」と宣言した。
そして、ナンバー1か2になるという目標を達成できない事業部門は刷新したり売り払ったりすることで、利益を増やしつづける計画だと発表したのである。このスピーチが強力な引き金となって、マネジメントスタイルの重点は一気に短期業績の方向へと傾いたのだった。
ウェルチがCEOの座に就いた1981年には250億ドルだったGEの収益は、退任した2001年には1300億ドルに増えていた。不幸なことに、この驚異的な成功の大部分は短期主義によってもたらされたものである。
膨らみつづけるアナリストたちの期待に四半期ごとに応えるため、ウェルチは頻繁に、GEキャピタルの増えつづける収益をほかの部門の低迷事業の補填に当てた。ウェルチが1981年にトップに立つ前、GE全体の純利益に占めるGEキャピタルの割合はわずか6パーセントにすぎなかったが、それが1990年までに24パーセントに増えていた。
1991年、GEは時価総額で最大の企業になった。株式市場はGEの旅を高く評価したのである。ウェルチが2001年に引退したとき、GEは101四半期連続で成長を続け、GE全体の利益に占めるGEキャピタルの比率は42パーセントにおよぶと発表した。
ウェルチのあとを継いだジェフリー・イメルトも最善を尽くして成長を続けようとした。9.11同時多発テロ事件後の不況のさなか、全社の収益に対するGEキャピタルの重要性がさらに高まった。
住宅市場が活気づいていた2004年、GEキャピタルのさらなる成長を促すために、GEはWMC社を5億ドルで買収した。GEにはWMCが革新的な会社に見えたのである。WMCはサブプライムローン業者として6番目の大きさで、「住宅ローン担保証券」と呼ばれる商品を扱っていた。
2007年、サブプライム住宅ローン危機のあおりを受けたGEは10億ドルを失い、のちに司法省から金融危機におけるGEの関与に対して15億ドルの罰金の支払が求められた。その後、司法省との和解が成立し、GEキャピタルのポートフォリオの大部分を売り払うまで、10年以上にわたってサブプライム危機の余波がGEを苦しめつづけた。
どの市場でもナンバー1か2になるというビジョンを掲げていたGEは、明確な目標のないまま旅をしていたのである。市場でさえGEの主要事業について混乱していて、2005年には同社を製造業から金融業に分類し直したほどだ。イテレーティブ型のアプローチが、GEを私たちの知る電球会社からサブプライム住宅ローン会社へと拡大させたのである。
イテレーティブ型アプローチを採用することで、多くの場合でプロダクトの潜在能力が完全には発揮されなくなる。結果として、プロダクトは肥大化したり、断片化したり、方向性を見失ったり、不適切な指標に振り回されたりしやすくなる。
ツイッターが掘り当てた金脈
しかしときには、ローカルマキシマムを目指すそのようなイテレーティブ型のアプローチが金脈を掘り当てることもある。そのような成功例があるため、このアプローチはビジネス慣行に深く根付いていったのである。ツイッター(Twitter)の誕生がその好例だろう。
同社は、もとはオデオ(Odeo)という名で2005年にポッドキャスト企業として設立された。しかしその年の秋にアップルがビルトインタイプのポッドキャスト用プラットフォームを搭載したiTunesを発表した。この出来事により、オデオの未来が閉ざされたのは明らかだった。
創業者たちが従業員に新たなビジネスのアイデアを募ったとき、オデオでエンジニアとして働いていたジャック・ドーシーが、人々が最新の情報をグループと共有できるプラットフォームのアイデアを披露した。
ユーザーに好評だったこのアイデアのイテレーティブ型アプローチから、マイクロブログのプラットフォームとしてツイッターが発展したのである。オデオの失策に対応するためにローカルマキシマムとして大急ぎでつくったツイッターが、たまたま金脈を掘り当てたのだ。
イテレーティブ型アプローチの成功例は読んでいて楽しいかもしれないが、このアプローチを用いて大儲けにつながったプロダクトがひとつあれば、その裏にはメディアで報道されることすらない無数の失敗作の墓場が広がっている。
著者も陥ったイテレーティブの罠
そう言う私も、イテレーティブの罠にはまったことがある。ドットコムバブルで好景気が続いていた2000年、私は共同創業者として初めてロビー7というスタートアップを立ち上げた。「ワイヤレス革命」をビジョンとして掲げ、Wi-Fi接続機能をもつ携帯電話や携帯情報端末(パームパイロットのようないわゆるPDA端末)向けにワイヤレスアプリケーションを開発した。
私たちはサービス企業だったのでさまざまな業界でニーズを探ることができた。そうやってキラーアプリを見つけたのである。次に、そのキラーアプリに集中するために、企業の重心を製造に移す。今の言葉に置き換えるなら、プロダクトマーケットフィット(顧客を満足させる製品を正しい市場に提供していること)を見つけるまでイテレーティブ型アプローチを続けることが、私たちの計画だったのだ。
クライアントのためにワイヤレスアプリをつくるという旅の途上で、私たちは電話にキーボードやタッチスクリーンがないと、どんなアプリもとても使いづらいという事実に気づいた。文字を入力するために数字キーを使うのは時間のかかる作業だった。
スマートな技術者集団だった私たちは、「音声とテキストの両方を使ってデバイスと対話できないだろうか?」と考えた。だが、当時のデバイスは音声認識ができるほどの演算能力が備わっていなかったので、実現するのは難しかった。それでも私たちは数々のハードルを乗り越え、携帯電話上で音声認識を可能にした主力プロダクトを開発したのである。いわば、シリ(Siri)の前身だ。
資金提供を受けているほかの多くのスタートアップと同じで、私たちも何がうまくいきそうかを見定めるために、数多くのプロダクトとビジネスモデルを次々と、つまりイテレーティブに試した。最終的に面白い技術の開発には成功したが、不況を乗り切ることはできなかった。イテレーティブを繰り返すうちに資金が尽き、ロビー7は音声認識技術目当てで買収された。
ロビー7で一攫千金とはならなかったが、私は貴重な教訓を得た。同様にイテレーティブだったふたつのスタートアップにかかわったあと、私は2003年にアビッド・テクノロジーの放送部門に加わることになった。そこで、プロダクトづくりに関してまったく違う戦略に出会った。
アビッドのビジョン駆動型アプローチ
アビッドの名はハリウッドの映画スタジオ界隈で広く知られていた。アカデミー賞にノミネートされる映画のほとんどすべてが、同社の「Avid Media Composer」というソフトウェアで編集されていたからだ。
そして当時、アビッドはソニーによって支配されていた放送ニュース市場に参入しようとしていた。2003年のテレビニュース素材はいまだテープに録画されていて(そのほとんどがソニー製のテープ)、ソニーの機器を使って放送用に編集されていたのだ。アビッド・ブロードキャストの責任者だったデビッド・シュライファーは、「完全にデジタルなニュースルームでテレビニュース制作を一変させる」というビジョンを抱いていた。
ニュースを編集する際、制作スタッフはストーリーに文脈やインパクトを付け足すために、関連する古いニュースを探して、その一部を抜粋して編集に加える。しかし、ほかのチームがつくったビデオテープを手に入れるのも困難だったし、望み通りの映像を見つけるのも、それを新しいニュースに組み込むのも容易ではなかった。
ライバル企業のほとんどはテープ中心のワークフローをそっくりそのままデジタルのフォーマットに置き換えようとしたが、私たちはデジタルプロダクト群を新たに開発することで、まったく斬新で、しかも以前よりはるかに容易なワークフローを提供することをもくろんだのである。デビッドは、もし魅力的なプロダクトの開発に成功できれば、どの放送局もいっせいにテープに別れを告げるだろうと確信していた。
私たちはプロダクト群を段階的に開発し、およそ1年にひとつのペースで新プロダクトを追加していった。データストレージの「Avid Unity」、ビデオの検索および共有ツールである「Avid Media Manager」、ストーリーを放送用に準備するための「Avid Airspeed」などだ。
開発は慎重かつ着実に進み、劇的な転換点もなかった。私たちはビジョンステートメント用の覚えやすいスローガンを繰り返すのではなく、困難をしっかりと理解して克服することで前進を続けた。
唯一の問題は、そこで働く私たち自身が、アビッドは私たちの仕事にあまり積極的に投資していない、と感じていた点だろう。開発リソースの不足を補うため、私たちは顧客の力を借りることにした。まったく新しいデジタルワークフローの価値を理解し、そのために追加料金を支払うことをいとわない顧客とパートナーシップを結ぶことで、機能を追加していったのである。
顧客と密接な関係を結び、ワークフローに対する顧客のニーズを探り、プロダクト群に欠けている要素を見定めることが、私の役割だった。隙間が見つかれば、それを埋めるための追加機能を開発する。要するに、私たちにとっては顧客が研究開発部門の役割を担っていた。
しかし明確なビジョンがなければ、このやり方が成功する可能性は低いと言える。ひとりの顧客が求めるニッチな機能を付け加える作業に追われることになるからだ。すべての顧客のそれぞれに100パーセントカスタマイズした機能を提供していては、売上の増加を通じてローカルマキシマムを見つけることはできるだろうが、総合的なプロダクト開発という点では意識が散漫にならざるをえない。カスタマイズされたプロダクトは長期的に生きつづけることはないだろうから、長い目で見れば、顧客にとっても不利になる。
そこで私たちは代替案として、私たちのビジョン――テープの不便さを解消してテレビニュース制作に変革を起こす手段としてのデジタルワークフロー――を買うように顧客を説得した。
それからの5年でアビッドは放送市場を支配し、ほぼすべてのテレビニュース制作会社(アメリカのNBC、CBS、ABC、カナダのCBC、イギリスのBBCやITVなど)がアビッドのプロダクト群を使うようになった。デビッド・シュライファーのビジョン駆動型戦略が功を奏したのである。
興味深いことに、人々との交流の場でもこの戦略の成功が実感できた。アビッドでは、ちょっとした飲み会やパーティーがあると、社のプロダクトや経営決断に関する議論が熱くかつ友好的に繰り広げられる。
数年後、アビッドの元従業員たちの集会が開かれたときも、私たちは古巣について熱心に語り合った。一方のロビー7では、スタッフが集まっても仕事の話はあまりしなかった。イテレーティブに追われていた私たちは、目的に対する深い信念を持ち合わせていなかったのだ。
ビジョンを日々の行動に落とし込むこと
念のために記しておくが、イテレーティブ型アプローチを批判しているからといって、イテレーティブの大切さを否定するつもりはない。この10年、私たちはアイデアを直接市場で次々とテストしながら顧客の望みを理解し、プロダクトを迅速に改良すること、言い換えれば、フィードバック駆動のイテレーティブが有効であることを知った。つまり、イテレーティブの力を利用する方法を学んできた。
しかしながら、ビジョン駆動型のアプローチは、今のところまだ確立していない。その結果、イテレーティブな能力が私たちの旅の移動を速めてくれたのに、目的地の設定やそこまでナビゲートする能力のほうが、その進歩に追いついていないのである。
もしあなたが「北へ向かって最高の旅をする」というおおざっぱなビジョンをもっているのなら、フィードバックにもとづくイテレーティブ型のアプローチで、あなたはボストンに、場合によってはトロントにたどり着けるかもしれない。一方、ビジョン駆動型のアプローチを用いれば、ビジョンがイテレーティブを駆使してあなたを望みの場所に運んでくれるだろう。
これまで、ビジョン駆動型のアプローチに通じる道には霧がかかっていた。優れたビジョンとは野心的でBHAG(Big Hairy Audacious Goal:巨大で困難で大胆な目標)でなければならないという認識が一般にあるが、この考えがこれまで多くの人を道に迷わせてきた。とにかく何らかのビジョンがあればビジョン駆動型のプロダクトをつくれる、というわけではない。ビジョンづくりに根本的に挑まなければならない。
大切なのは、優れたビジョンをもち、それをシステマティックに日々の行動に置き換えること。短期的なビジネスニーズと長期的な目標は競合することが多い。そうなると、意識が短期的なビジネスニーズに奪われるので、ローカルマキシマムを優先し、グローバルマキシマムを見失いやすくなる。つまり、ビジョンができたなら、ビジョンを追いつづける態勢を整えなければならない。
本書は、ビジョン駆動型のプロダクト開発を行い、よりスマートにイノベーションを起こすのに欠かせないマインドセットを手に入れる方法を示す。
プロダクトリーダーになる道のりで、私は役職や業界に関係なく、誰もがプロダクト思考を身につけ、系統だったやり方でプロダクトを開発することができると気づいた。私は、メディアとエンターテインメント、広告技術、研究、統治、パブリックアート、ロボット工学、ワインなど、さまざまな分野でプロダクトを開発してきた。
実際、私が請け負ってきた仕事のどれもが、それぞれ異なる業界に属していたと言える。私が担ってきた役職も、マーケティング、戦略、プロジェクト管理、運営、CEOなど、同じように多岐にわたっている。そうしたさまざまな経験を通じて、私はプロダクトとは役職や職務ではなく、考え方なのだと理解した。
非営利組織、政府機関、サービスプロバイダー、研究部門、ハイテクスタートアップ、フリーランス……どこで働いていようと、そこにはプロダクトがある。具体的な物品や仮想的なモノだけを製プロダクト品とみなす考え方はもう古いのだ。
ラディカル・プロダクト・シンキングとは、世界にどんな変化をもたらしたいかを考えながらグローバルマキシマムを探し求める態度を指す言葉だ。したがって、あなたのつくるプロダクトはその変化をもたらすための改善可能なシステムである。
ラディカル・プロダクト・シンキングでは、プロダクトはそのプロダクトが引き起こすべき変化のビジョンによって導かれる。ラディカル・プロダクトはビジョンから生まれ、明確な理由があって存在する。この存在理由が戦略や優先順位、そして実行計画と組織の文化を決定する。
ラディカル・プロダクト・シンキングが組織にこのマインドセットを育むガイドとなり、最終的には誰もがビジョン駆動型のプロダクトをつくれるようになる。