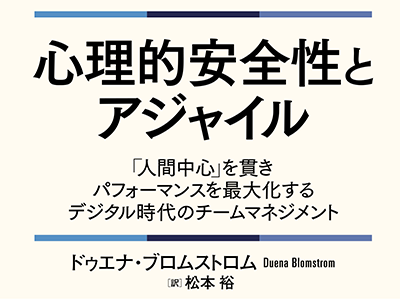本記事は『心理的安全性とアジャイル 「人間中心」を貫きパフォーマンスを最大化するデジタル時代のチームマネジメント』の「第7章 次になにが起こるのか、そしてパンデミック以降の世界での働き方」から一部を抜粋したものです。掲載にあたって編集しています。
リモートvs.柔軟(どこでvs.どうやって)
もっとも一般的な誤解のひとつが、「リモートワーク」「在宅勤務」「柔軟な働き方」がすべてまったく同じものだという考え方だ。実は、そうではない。最初の2つはパンデミックの観点からは同義語とみなしてもいいかもしれない(ただしそれ以外の観点ではそうとは限らない)が、「リモート」と「柔軟」はまったく互換性がない。実は、リモートの性質は柔軟の特徴のひとつにすぎず、その概念の中に厳格に留められているものなのだ。
柔軟な働き方とは、従来型のオンサイトや出勤仕事とは違う形でおこなわれる仕事のことを言う。そしてこれはその仕事がおこなわれる場所と方法の両方を指す。どちらか一方だけを議論するのではなく、場所とプロセスの両方が、このトピックには含まれている。
そして、ここに含まれる概念がパートタイム、期間限定(学期の間など)、ひとつの仕事を複数人で分担するジョブシェアリング、アウトプットベース(今後数年間で多くの企業が注目しなければならなくなる、もっとも興味深い概念のひとつだ)、圧縮労働時間(2018年にニュージーランドで実施された週4日労働の実験では、生産性が20%向上することが証明された)、そして中でももっとも興味深いのがフレックスタイム、つまり従業員が雇用主との合意に基づき、一定の期間内でいつ仕事を始めていつ終わらせるかを自由に選べるようにするというものだ。
ここに述べた働き方のバリエーションはそれぞれ、仕事の効率や生産性を大幅に高める能力について膨大な量の調査研究がおこなわれており、ほとんどの調査結果は30%以上の改善が見込めるとしている。理由を分析すると、主な原因は従業員満足度ややる気にあり、したがってパフォーマンスの大幅な向上にあるが、かつてはストレスや不安、鬱など、圧倒的に仕事に関連して発生していた病欠や退職が減ったという事実もある。
とはいえ、パンデミックという環境において、COVID-19が世界を変えたときに議論され、実施された唯一の変化は、働く場所についてのものだけだった。言い換えれば、特定の職場のモデルにほかのバリエーションがあり得るのかどうかを知るためにおこなわれるべきだった発見や調査、デザイン、交渉などは一切なかったということだ。
このため、もともと出勤して働いていた従業員は自分たちの仕事を在宅勤務に切り替える方法についてたいした研修もなく、数多くの落とし穴をどうやって避ければいいかのまともなアドバイスもないままに、プールの一番深いところで手を離されることになった。
その中でも大きかったのが、家事と仕事の連続性の感覚が非常な重荷となり、両方を満足させようとどれだけがんばっても、どれだけ働いても自分は無力だと感じる従業員が多くいたことだ。意図的な個人の領域がまったく明確に設定されない状況に置かれ、この新たな環境で不満を吐き出す場もたいしてなく、雇用が確保されているという保証もますますあやしくなる中、彼らはあっというまに疲れ果ててしまった。
ここでもまた、パンデミック以前からすでにリモートワークの習慣を身につけていた人々がロックダウン中は有利だった。彼らはリモート環境でも生産性を維持できるようにさまざまな要素を考慮して仕事のプロセスを確立しており、多くが実際に、経験によって築き上げた柔軟な働き方を習慣としていたのだ。
だが突然リモートになった従業員の多くが、自分でスケジュールを立てたり、自宅で持続的に仕事をしたりできるような自分なりのパターンを編み出すための指針をまったくもらえなかった。ただ家の中に場所を作り、そこからいつ終わるとも知れないいくつものミーティングやZoom通話に引きずりこまれ、さらにはきりのない電子メールの応酬と混乱の渦に巻きこまれた。そこに子どもの自宅学習まで加わり、状況はさらに複雑になっていった。
企業も従業員もこの状況が一時的なものですむと信じていたため、短期間はこれでもなんとかうまくいった。だが数週間が数カ月になるにつれ、もはやこれが非常手段ではなく、ひとつの生活様式として扱うべきなのだということが全員にとって明らかになってきた。
こうして、強制的ロックダウンに入ってから数カ月後、持続可能性をめぐる問題とそれに伴う個人的限界や肉体的・精神的制約が浮上し始め、オンラインで率直な対話がおこなわれるようになった。残念ながら、これと共に起こったのが「オフィスに戻る」可能性についての議論だった。未来のハイブリッド方式の周辺で混乱が収まりもしないうちに出てきたこの議論と、これから起こる極端な不況についての報道も相まって、柔軟な働き方の「なぜ」と「どうやって」をめぐる率直な対話の多くはまたしても「どこで」、さらにはもっと痛烈でどこまでも恐ろしい「もし」という問題の周辺に閉じこめられてしまった。
2020年も後半に入り、不況が大規模になり得る可能性が明確になってくると、自身の限界について語ったり、組織に敬意や気配りを求めたりしようとする人は少なくなった。仕事があるだけでもありがたくてたまらないという感じだったのだ。自分がいつでも使い捨て可能だという身のすくむような恐怖にかられて、人の倍の時間働き続けていると、自分がもっとも生産的になれる最善の時間や方法を見つけるために必要な思考など要求することはない。
むしろその逆だ。加えて、片親、もしくはフルタイムで働く両親と子どもという家庭では、ロックダウンが1、2週間ですむ話ではなく、場合によっては何カ月にも延びることになるのが明らかになると、その負担は説明しようもないほど大きくなっていった。
最初のころ、育児と家庭学習が有意義な形で議論されることは驚くほど少なかった。せいぜいふわふわとしたミームが登場し、笑える状況を嘆く意見記事がときどき出てくるくらいだったのだが、極度の疲労と心の健康という全体的な問題も当然加わって(したがって生産性の問題も加わって)、長期的にはその影響が当時想像し得たよりも総じて大きな困難になったのも不思議はない。
時間が経つにつれ、この懸念はますます鮮明になっていった。家事と家庭学習のプレッシャーに直面し、柔軟な働き方を選べるだけ幸運だった多くの親が過剰に働き、真夜中すぎまで(もしくはその時間から)働くようになった。そうなると当然、極度の疲労に陥るリスクが急激に高まる。ほとんどの企業でほとんどのチームが明確なコミュニケーションも方針も指針もなく、自力でなんとかするしかない状況に置かれていたため、この傾向は顕著だった。
そうした指針が少しずつ生まれ始め、「ニューノーマル」のモデルをめぐる混乱が落ち着いてきたのは、2020年夏になってようやくだった。職場ではすばらしい実績を上げていたのに教師としての役割では標準に達することができず、少しでも権威があるように見せかけながらテーブルの下でこっそりググっているようななりすまし症候群が蔓延するため、優秀な人材ほど苦労することが、経験的にわかってきた。
加えて、いつもの「仕事ばかりのママでいることの罪悪感」が今度は性別を問わずどちらの親にものしかかるようになり(ただ、もしちゃんと調べれば、パンデミックの最中は仕事の状況にかかわらず、男性よりも女性のほうが家庭学習の仕事を引き受けていた可能性が高い)、誰もがますます疲労困憊し、まるで教師と社会人として「生存者の罪悪感」と「なりすまし症候群」両方の初期の形と戦うのに躍起になっているように感じていた。
リモートとワークライフバランス
歓迎をもって受け止められるこのワークライフバランスという用語に関して、おそらくもっとも興味深いと言えるのはAmazonのジェフ・ベゾスの意見かもしれない。彼はワークライフバランスをまったく信じていないことで有名だ。「ワークライフバランスについてはいつも質問されるよ。僕の意見では、それは消耗させる言葉だ。そこに厳密な相殺があることを示唆する言葉だからね」。
仕事と私生活をバランスを取るべき行為としてみなす代わりに、ベゾスはそれらを2つの統合されたパーツとして見たほうが生産的だと語った。「実際は円なんだ。バランスじゃない。この仕事と私生活の調和ってやつは、僕がAmazonでも若い従業員や、実際には上級幹部にも教えようとしていることだ。特に、新しく入ってくる人たちには教えたいことだね」。そして、彼は職場での作業と家での作業、そして娯楽での作業を、自分にとって一番うまくいくと思うリズムにミックスするそのやり方について説明した。
2020年のパンデミックの影響が職業人として、また一個人としての私たちになにかを教えてくれたとすれば、それはオンラインでの交流や仕事をどのように構成するかについて考えることには時間を費やす価値が間違いなくあるということだ。正気を保って長期的に生産性と競争力を維持するためには、他者に対してだけでなく自分自身に対しても思いやりを持ち、誰もが同じ働き方をするわけではなく、誰もがそれぞれ異なる、だが同じくらい大事な限界を有することを認識する必要が今まで以上に出てきた。
その限界に気づき、理解し、そして互いにコミュニケーションを取り合うために時間をかけるべきなのだ。
もちろん、自分がどんな仕事をどのくらい長く、いつするかを好きに選べる贅沢が誰にでも与えられているわけではない。無限に続くミーティングのメリーゴーラウンドに乗っているように感じる者もいれば、自分の本来の限界をとっくに超えてしまったと感じる者もいる。落胆と不安の感情が深刻化すればするほど、見通しはますます暗くなっていった。
もっと有能なプロフェッショナルができる範囲でやっていたのは、自分の能力を正直に見直し、「もう無理」という限界に近づいたらそれに気づけるようにするということだった。いったんそれが明確になると、自分本来の自然のリズムと交流面での精神的・感情的能力、つまり自分が気持ちよく対応できる範囲をチームやチームリーダーに勇気をもって伝えるための時間を取るのだ。
一部のリーダーは耳を傾け、チームによってはクライアントや納期による制約がある中でもこのような人々から学んだことを調和させられるような、真に柔軟な職場環境を共創することに時間を費やした。個々の仕事は時間の制約なしにできるようにしつつ、共同作業やチームワークは合意された時期におこなわれるようにしたのだ。
すべてのリーダーがこうした深い洞察を部下の個々の働き方に組み入れるべきだと(あるいはそれができるのだと)気づいていたわけではないが、そのことを伝えるという行為だけでも、心理的不快感を少し和らげることができる。
リモートワーカーの大多数が、自分の真の限界を発見する「許可」を与えられていると感じたことが一度もないか、それに気づく時間を取ったことがないか、それを伝えることでただでさえ大変な職場で「波風を立てる」のは建設的ではないと感じていた。だがそれ以上に不況と失業に対する絶望的な恐怖からそうすることができず、その結果、とにかく絶対にそのことについて発言しない状態だった。
先見の明に富んだ数少ないチームリーダーたちは、急にリモートになった部下たちが自らを見つめ直し、セルフケアに注力する必要性を訴えてきた。彼らは個人の限界を無視することは許されない、それどころか長期的には無責任にさえなる行為だと強調した。チームメンバー1人ひとりと1対1の面談(1on1)をおこなう継続的なキャンペーンに注力する時間を取り、共同のミーティングでも質問したし、正しい会話を引き出した。
最終的に、彼らはチームの再立ち上げの段階でカルチャーキャンバスも使い、リモート環境におけるチームの柔軟な働き方を定義する上で一番うまく機能するツールや、プロセスをめぐる交流のための契コントラクティング約作成の一部として議論した。これにより、内省と率直な会話には価値があり、競争力を保つためには必要なのだということが強調された。
彼らは部下に対し、自分の負担の限界がどこにあるかを知ることに時間を費やすよう奨励した。快適かつ生産的に取り組めるオンライン交流(特にビデオ通話)の時間は従業員1人ひとり異なり、それを超えると単なるプレゼンティーズムになったり、単なる確認手続きになったりして、取り組む価値はまったくない。
どこからが「もう無理」の範囲なのかを全員に定義してもらい、教えてもらうという方法は、パンデミックという恐ろしい外的状況の真っただ中、著しくデジタルな環境で健全な働き方を構築することに心から関心を持つ一部のリーダーにとっては、とてつもなく有益なものだった。
これが実現し、従業員が自らの限界を伝え、チームがそれに対応できるように再構築され、契約を作成し直し、柔軟な働き方に対する明確な許可が与えられた場合でも、教訓としてはやはり、重要なのは従業員個人がそこから時間を管理し、自ら動き、自分の生産性や成長、幸福度を高める技術を磨くことだと言える。
これを理解した者は明確で善意に基づく、しっかりと構成されたスケジュールを組み、チーム内で決めたリモートワークや柔軟な働き方の自由さの中で自分が正気を保って機能的であり続けるために強く求められる骨組みとして、そのスケジュールに従うだろう。
当初、これらのスケジュールの多くは職場と家庭とで同じように扱われていて、特定の時間をすぎたり週末になったりしたら一切仕事はおこなわれないと宣言していた。だが、ロックダウンの数カ月間、子どもの宿題を見ている最中でもメールの1通や2通はもぐりこませられるし、バルコニーで昼食を取りながら外を眺めている最中のほうがSlackで気さくな会話をしやすいということに人々が気づき始めると、その境界線は曖昧になっていった。しかし、よりパフォーマンス重視の人々は、前述のベゾスによるモデルのほうへと仕事が移っていっても必要であれば休憩をちゃんと取り、自分がもっとも生産的になれるゴールデンタイムに集中することができた。
それ自体、個人レベルでの柔軟な働き方の背後にある大きな気づきで、燃え尽き症候群に対する唯一の特効薬だ。つまり、自分がインスピレーションを感じる瞬間に対する自然のリズムを持ち、それに合わせて最高の仕事をする権利があるということだ。ただし、そうした瞬間が、他者との直接の交流なしに可能である限りにおいてだが。
なにをするにしても、私たちは最高の仕事をしたいと願っている。そして自分が抜群に集中でき、すばらしいアイデアが満ち溢れ、生産的になれる瞬間が明確にわかる。そうしたときこそ、そのような瞬間が訪れない1週間よりも高い品質を、たった1時間の仕事の中に詰め込めるのだ。自分の精神的健康にとって自然なリズムでそれが実践できれば、私たちは負担を抱えすぎ、最終的には苦しみながら、疲労困憊して地面に倒れこまなくてもすむ。
したがって、このように個々人の状況やさまざまなリズムのためにスペースを空けることには、パンデミック後、そして不況後のすべての会社が真剣に取り組むべきだ。ITコンサルティング企業Synechronの最高人事責任者ジョン・ゴーントは言う。
「自宅で仕事をしている従業員にとって、マルチタスクというのは通常業務に加えて病気を抱えた高齢の親の世話をし、乳幼児の面倒を見、さらに家事労働もこなすということだ。つまり、雇用主は従業員が怒りっぽくなったりイライラしたり、やる気を失ったり仕事を先延ばしにしたり、常に沈んでいたり、過剰に心配したり不安がったり、よく眠れていなかったり、独創性やイノベーションに欠けていたり、マイナスあるいは悲観的思考になっていたり、薬の使用・乱用が増えたり、無鉄砲な行動に出たりさえするなど、数々の兆候を見逃さないように目を光らせていなければならない」。
パンデミックの最中、在宅勤務に対する従業員の態度に影響を与えた要素がいくつかある。
- 仕事の性質──個人の貢献が何割で、連携を必要とするのは何割か
- 必要なITツールや十分なコミュニケーションへのアクセス
- 実績や成果を明確に示せる能力
- 家庭環境──子どもの家庭学習が加わった従業員は2つの仕事を抱えることになり、一方の仕事に関してはうまくこなせないことを自覚する。これは、調査によると、優秀な人材ほど重荷に感じるようだ
- 過去にリモートワークの経験があるか
- 回復力の既存のレベル
- 個人レベルとチームレベルの両方について、柔軟な働き方と自己決定に対する企業の姿勢
- 仕事の量と生産性に対する個人の能力――加えて、自分の限界を理解してそれを他人に伝える意思
- 性格──内向的な人と外交的な人とでは、在宅勤務の能力に対する反応が異なっていた
- 経営陣からの支援のレベル──中間管理職が管理権を失ってパニックに陥っているか、あるいは人間中心の行動に注力し、支えてくれるサーバント・リーダーがいるか
- 個人の時間管理と自発性のスキル
- 「この時期に自分の限界について考える許可」の認識──これは年功に関係するとも言える。従業員がベテランであればあるほど、自分には価値があるのだから敬意をもって扱われるべきだ、個人のニーズに合わせてカスタマイズされた職場環境を要求する権利があるのだと感じる可能性が高いからだ
- チームにおける心理的安全性の過去のレベル
- EQの既存のレベル──オンラインで他者の感情を読み取り、自分の感情を表現できることは、近接性と前後の文脈がないと実際難しい
オンラインで、握手もできないとなると、私たちはもっと感情的知性を高め、もっと鋭く、もっとつながって、もっとチームダイナミクスに注力し、もっと業務に集中して、現実世界でのビジネス交流の儀式にはあまり気を取られないようにする必要があった。
数通のメールやSlackのスレッド、あるいはビデオ通話から誰かの心の状態を読み取らなければならなくなると、突如としてもっとしっかりと注意を払い、これまで以上に強い共感力を発揮しなければならなくなった。そして、乳幼児が30回目の「ママ!」や「パパ!」のあとに緊急事態――かなり切羽詰まった(そしてたいていは「ばっちい」)状況――を要請する発言をしたためにミーティングを途中退室しなければならなくなると、結局は私たちが認識している「ワークライフバランス」の概念を考え直すことになった。そして、重要なこと――発言しても安全だと感じられる範囲内であればどこでどのようにやるかは関係なく、やるべき仕事とそれを一緒にやる人々――に意識を集中するようになった。
仕事の未来の「どこで」や「どうやって」といった正確な詳細はともかく、これがパンデミックのもたらした純利益だ。リモートの概念の証明と柔軟性の概念の証明が各個人にあてはめられ、これからは常に各個人の限界や能力の範囲内で物事を考えなければならなくなる。したがってこれが、未来の偏在的なスキルになるのだ。
仕事にまつわるすべての個人的成長の習慣、EQ、そして人間への注力は、オフィスでしか仕事をしなかった時代が遠い過去の記憶となり、自分にとって最善の働き方がどんなものかを深く、しっかりと理解できる精神的な形と自尊心の持てる空間を確保するために私たち1人ひとりが投資をする、主にハイブリッドな未来において、プロフェッショナルでいるための必須条件となるだろう。