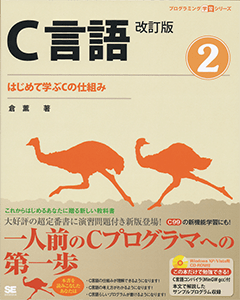C言語改訂版② はじめて学ぶCの仕組み
倉 薫 著
- 形式:
- 書籍
- 発売日:
- 2009年02月12日
- ISBN:
- 9784798118079
- 定価:
- 2,068円(本体1,880円+税10%)
- 仕様:
- B5変・320ページ
- カテゴリ:
- プログラミング・開発
- キーワード:
- #プログラミング,#開発環境,#開発手法,#Web・アプリ開発
- シリーズ:
- プログラミング学習シリーズ
一人前のCプログラマへの第一歩
本書では、C言語をたんに使えるということを目指しているのではなく、C言語で作られたプログラムが、コンピュータ内でどのように動作しているのかということを、しっかりと把握することを重視しています。それによって、C言語というプログラミング言語の設計思想、そして、それをどのように使いこなすべきかということを学んでいきます。なぜならば、C言語のしくみを本当に知る、ということが、優れたC言語プログラマを目指すために必要不可欠なことだからです。
C言語(1)に書かれていることは、確かに基礎としては重要です。ですが、「C言語
」という言語の思想として一番大事なことは、むしろこのC言語(2)に書かれています。私はこのC言語(2)にこそ、もっとも知っていなければいけないことを書いたつもりです。
この『C言語(2)』に書かれている内容をマスターすることによって、単純に「C言語を使えるプログラマ」から、「C言語を熟知して優れたプログラマ」へステップアップしましょう!
「はじめに」より抜粋
●付属CD-ROMのご案内
本書の付属CD-ROMには、本書で掲載されているサンプルプログラムとコンパイラ(MinGW gcc)が収録されています。
Windows XP / Vista 用。
第1章 C言語のしくみ
1-1 C言語のしくみ
C言語のいいところ
C言語の目的
コンピュータのしくみ
C言語のプログラムを実行したときのコンピュータの動き
1-2 変数
型の扱い
整数
符号付き整数
それ以外の型
サイズの知り方(sizeof演算子)
1-3 printf()徹底攻略
はじめに
幅をそろえる(整数値)
表示をそろえる(文字列)
実数の表示
10進数以外の形式での出力
符号なし整数
%c、%dでわかるコンピュータのしくみ
では文字型変数というのは何なのか
練習問題
第2章 データ構造詳細
2-1 定数(const)
「定数」とは
#defineとの違い
constのポインタ変数
ポインタ変数に対するconst
関数引数でのconstポインタ変数
constの落とし穴
返値のconstによる保護
2-2 ポインタ
ポインタについて
コンピュータ内部でのポインタの扱い
アドレス
NULLポインタ
ポインタのポインタ
2-3 配列
配列について
メモリで見た配列
構造体の配列
多次元配列
2次元配列の例
2次元以上の多次元配列
大きな配列を使うときの注意点(スタック)
2-4 ポインタと配列の関係
ポインタと配列について
ポインタと配列の関係
アドレスによる配列のアクセス
関数に配列を渡す
ポインタと配列の使い分け
2次元配列とポインタ
2次元配列を関数に渡す
2-5 構造体
構造体について
構造体の宣言
構造体の初期化
メモリで見た構造体
ビットフィールド
境界を合わせる
typedef
共用体
2-6 enum
enumについて
enumはなぜマイナーな機能なのか
妥協としてのプログラミング
enumの理想とする機能
enumの現実
enumの日常
練習問題
第3章 演算子
3-1 演算子
演算子について
論理演算(1)
2進数
論理演算(2)
&演算子、|演算子
^演算子
~演算子
<<演算子、>>演算子
3-2 その他の演算子
その他の演算子について
三項演算子
三項演算子の具体的な機能と使い方
三項演算子を使う際の注意点
キャスト演算子
キャスト演算子の使い方
カンマ演算子
演算子の優先順位
練習問題
第4章 制御構造
4-1 制御構造
制御構造について
goto文
goto文の機能
goto文が嫌われる理由
do~while文
4-2 ブロック構造
ブロック構造と暗黙のブロック
練習問題
第5章 関数
5-1 関数
関数の復習
返値の無視
返値を返さない関数
型の省略
引数の型変換
main()関数の引数
関数のスコープ
5-2 関数のポインタ
ポインタの利点
関数のポインタの使用頻度
関数のポインタ
関数へのポインタを使うときの注意点(その1)
関数のポインタ変数の配列
関数へのポインタを使うときの注意点(その2)
5-3 メモリの動的な取得
メモリとOSの関係
変数宣言の限界
malloc()関数
malloc()関数の利点
malloc()関数の失敗
free()関数
realloc()関数
練習問題
第6章 プリプロセッサ、リンカ、ライブラリ
6-1 プリプロセッサ
プリプロセッサ
コンパイラがコンパイルとする順序
プリプロセッサの役割
#define
引数付きマクロの良い点
引数付きマクロの注意しなければならない点
引数付きマクロの応用
#undef
#ifdef、#ifndef、#else、#endif
#error
組み込みマクロ
複数行にわたる命令
プリプロセッサマクロを使うときの注意点
6-2 リンカ、ライブラリ
複数のファイルを使ったプログラムの開発
複数ファイルのコンパイル
コンパイラのしくみ
ライブラリ
ライブラリへの関数の追加
ライブラリ内の一覧
ライブラリの中の.oの削除
ライブラリを使う
ヘッダファイル
あらかじめ用意されているライブラリ
練習問題
練習問題解答および解答例
お問い合わせ
内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。
正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや
その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。
利用許諾に関するお問い合わせ
本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。
書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。
現在表示されている正誤表の対象書籍
書籍の種類:紙書籍
書籍の刷数:全刷
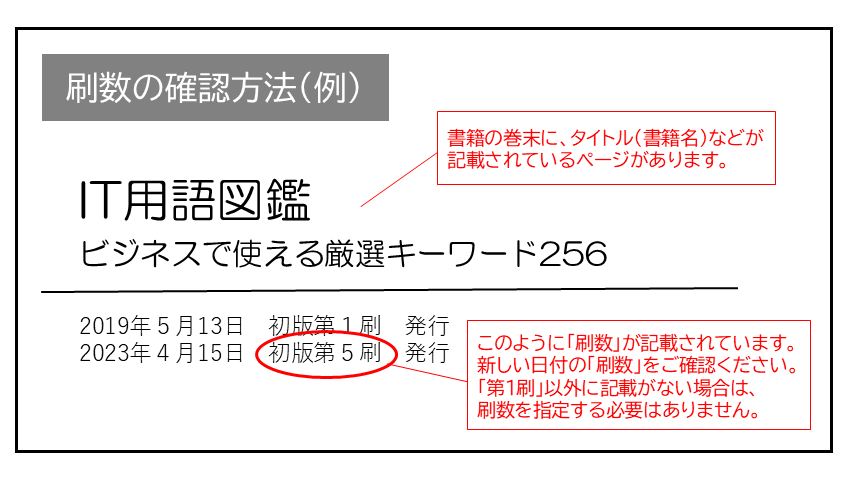
書籍によっては表記が異なる場合がございます
本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
対象の書籍は正誤表がありません。
| ページ数 | 内容 | 書籍修正刷 | 電子書籍訂正 | 発生刷 | 登録日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 2行目 |
|
未 | 未 | 1刷 | 2010.05.12 |